【東大生が語る】リビング学習はいつまで?|子ども時代〜大学院の勉強場所【塾なし独学で灘東大へ】
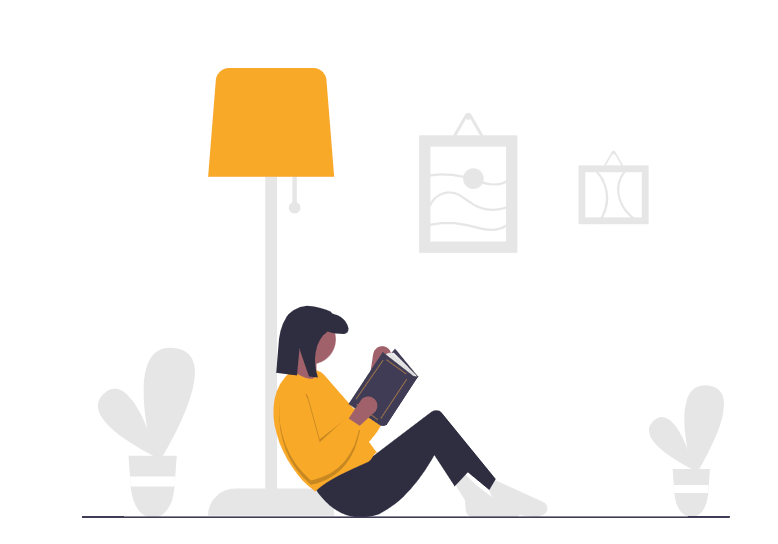
環境は何よりも大事だと思っています。
私たちは環境を作ることができます。
環境は私たちを成長させます。
今回は、私の勉強場所をご紹介していきます。
- 知育子育てを実践したい
- 読書好き、勉強好きな子どもに育ってほしい
- 子どもに伸び伸びと育ってほしい
- 子どもの能力を最大限に伸ばしたい
- 自宅に知的空間を創造したい
そんな方は今回の記事が役に立つはずです。
とりわけ、
- 息子視点で役立ったこと
も補足しながら紹介していきます。
このブログは以下の方に向けて書いています。
- 子育てをしている方
- (学生・大人問わず)勉強している方
- 子どもと接する機会のある方
よろしくお願いします!
こんな家庭で育った
本題に入る前に、ざっと私の家庭についてご紹介します。
- 父は教育学をしっかりと学んだ人
- 母は褒めるのが上手な主婦
それ以外は、ごく普通の一般家庭ですね。
ごく普通に地元の中高に進んで、大学に行ければ御の字だったようです。
それが人生わからないものです。
受験まみれになってしまうんですね。
当の本人(私)は楽しんで受験していたので、「結果よし」ということで。
↓まずは以下の記事から!
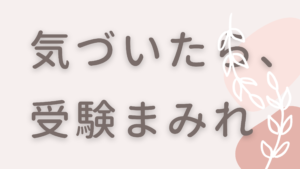
息子視点で教育・子育てについて語る(日本唯一の)ブログです。
親の子育てで良かったこと、役立ったことをどんどん書いていきます。
私の家について
田舎の一軒家です。
私が生まれてすぐに建てました。
設計・建築には父も参加したらしいです。
一階の居間はちょっと広い方だと思います。
台所とつながっており、大きな木の食卓があります。
二階には本を読むための和室があります。
それ以外は、ごく普通の部屋構造です。
幼児期|リビング学習+父の部屋
親と同じ部屋で勉強していました。
- 1階の居間
- 2階の和室
- 2階の父の部屋
これら3ヶ所になります。
勉強といっても、ひらがなの練習をしたり、簡単な計算をしたりです。
私の父は英才教育をするつもりはなかったようで、もっぱら絵を描いて過ごしました。
親がそばにいるだけで安心感が得られました。
また、
親が適切なフォローをしてくれるというメリットもありました。
適切なフォローというのは、自分の絵を褒めてくれたり、計算の答え合せをしてくれたりといったことです。
私の家庭は褒めて伸ばすタイプですので、褒めてくれる両親が近くにいるのが嬉しかったです。
小学低学年|リビング学習+父の仕事場
小学校に通い始めると、自分の机を買ってもらいました。
自分の居場所がもらえたようで、本当に嬉しかったです。
それは居間の隅っこに置かれました。
父の真似をして、辞書を開いたり、図鑑を開いたりしてはノートに書き写していたのを覚えています。
自分の机をもらったとは言え、引き続き親と同じ部屋で勉強していました。
- 1階の居間
- 2階の和室
- 2階の父の部屋
- 父の作業場
ひとつ異なるのは、1ヶ所増えたことです。
父の作業場です。
私は小学2年生の頃から、
- 自分で曜日を決めて学習する
ようになりました。
最初は、週2で始めました(火曜と金曜など)。
自分で決めた学習の日は本気モードでの勉強です。
その場所に選んだのが、父の作業場です。
メリットはやはり、
- 親の働く姿を間近に見られる
ということです。
電話応対が入るなど多少の雑音はありますが、それさえも自分のモチベーションと集中力を高めてくれました。
小学高学年|父の仕事場+自分の部屋
生まれて最大のプレゼントをもらいました。
自分の部屋です。
2階に設けられました。
飛び上がって喜びました。
それに伴って、私の机が1階の居間から2階へと移されました。
私の勉強場所は少し変わりました。
- 1階の居間
- 2階の和室(←毎朝の読書)
- 父の作業場
- 2階の自分の部屋
メインの勉強場所は父の作業場です。
小学高学年になると勉強する曜日も時間も一気に増えました。
勉強が楽しくて仕方がありませんでした。
次第に、
- 父と根気比べをする
ようにもなりました。
どちらが真剣に勉強(仕事)できるか勝負です。
父はよく、
- ガクの粘り強さにはかなわんな〜
と言いながら、仕事していました。
その言葉を聞くのが楽しみで、ますます集中して勉強するようになりました。
小6(中学受験)
何を思ったのか、中学受験というイベントに興味を持ちます。
参加するには本気で取り組みます。
乗り気でなかった父もどういうわけか、全力でフォローしてくれました。
模試と講習会は塾のお世話になりましたが、それ以外は自宅学習です。
- 1階の居間(←ときどき)
- 2階の和室(←毎朝の計算・暗記特訓)
- 父の作業場
- 2階の自分の部屋
- 塾(←模試と講習会)
勉強場所は今までとほとんど変わりません。
毎朝の読書タイムは計算特訓と暗記特訓に変わりました。
うぅ…。
貴重な読書時間が…。
中学時代|自分の部屋
さっそく塾に通っている友達がたくさんいました。(大丈夫?)
私はこれまで通り、自宅学習を続けます。
まったくお金かからないので、独学は本当にオススメ。
勉強場所は減りました。
- 1階の居間(広い食卓が便利)
- 2階の自分の部屋
- 列車の中(宿題)
この3ヶ所です。
私は気が散るようなモノを持っていなかったので、自室でも常に最大限の集中力を投下することができました。
中学入学祝いとして、立派な椅子を買ってもらいました。
座り心地が完璧すぎて、パフォーマンスが10倍上がった気分です。
同時に父の作業場で勉強しなくなりました。
理由は単純です。
参考書や問題集の量が一気に増えてきて、家と父の作業場の行き来が面倒くさいからです。
また、時間を有効活用するために行き帰りの列車をフルに使っていました。
学校の宿題を家でしたくなかったので、鬼のような集中力で取り組んでいました。
追記
宿題に熱中しすぎて最寄駅に着いても気づかず、何回も乗り過ごした…。
高校時代|自分の部屋
勉強場所はさらに減りました。
- 2階の自分の部屋
- 列車の中(英語リスニング)
いろんな問題集やら参考書やらを机目一杯に広げて勉強していました。
満員列車にさらされた往復4時間はあまりいいことはなかったです。
本も開けないので、ウォークマンでひたすら英語を聞いていました。
大学時代|図書館
上京しました。
自分の「住所」を持ちました。(←普通のアパート)
部屋は一気に狭くなりました。
- 自分の部屋(主に読書)
- 大学の図書館
勉強は自分の部屋か大学図書館の自習室で行っていました。
家にネットを引いていなかったので、パソコンを使うときは大学図書館を利用していました。
人が多すぎるのが難点ですが、雰囲気が好きです。
大学院(いま)
自然豊かな環境を求めて少し離れたところに引っ越しました。
最高すぎです。
ウグイスの声で目覚めます。
これほど素晴らしく幸せな生活が待っているとは思いませんでした。
勉強場所は以下の通りです。
- 自分の部屋(自分の勉強)
- 研究室(研究関係)
- 大学図書館(ときどき)
- 列車の中(読書・情報収集・アウトプット)
大学の勉強を自宅へ持ち帰らないようにしました。
こうすることで、明白に線引きすることができます。
自分の勉強と大学の勉強の2つの路線で進めています。
また、列車の中では情報収集をしています。
始めて日が浅いツイッターも基本的に移動中のみです。
なお現在も自宅ではネットなしの生活をしています。(スマホのみネット接続。これがいいのだ!)
最後に|親のそばで勉強するということ
黙って見守ってくれれば、それで大丈夫です。
そばに誰かいることで、自制が働きます。
見られていると感じると、いい姿を見せようとします。
私の幼少期の自宅学習が成功した理由は主に次の2点です。
- 親の気配を感じられる場所で勉強していた
- 親が熱心に仕事(家事)をする姿を間近で見られた
私の父は仕事熱心でした。
私の母は料理熱心でした。
だからこそ、
私は勉強熱心になりました。
ロールモデル(規範となる人)が身近にいると、それを真似しようとします。
逆に言えば、
身近な人が怠惰であったり、そもそも身近に模範的な人がいなかったりすれば、成長の伸びも鈍化されるように感じます。
私の場合は、とりわけ父が目指すべき理想像として好影響を与えてくれました。
それでは!
関連記事
以下の記事もご覧ください。
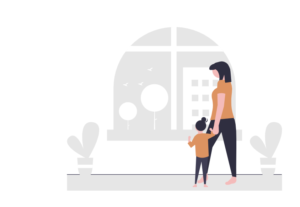

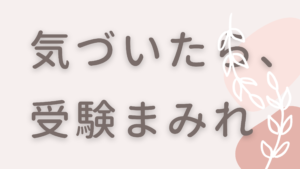
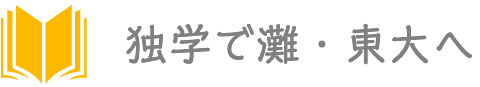

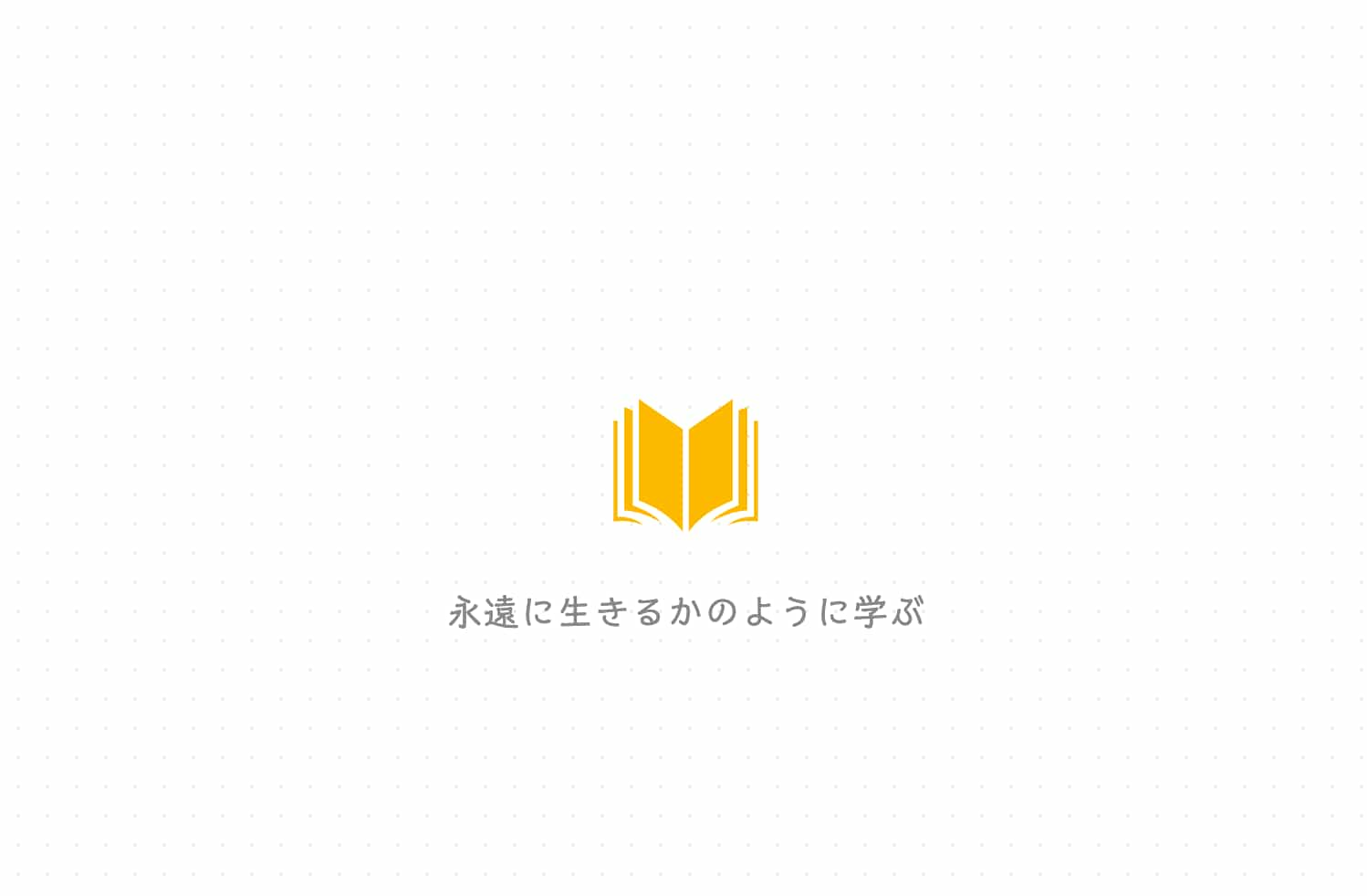

コメント