【子育て】東大の先生の勉強法【父が語る】

最も尊敬する人は?と聞かれれば「父だ」と即答します。
普通の人ではありませんでした。
自分に厳しくて他人に優しい父が格好良かったです。
誰よりも尊敬しています。
自分が目指すべき人です。
今回は、地元の子どもたちに向けて書いた父の文章をご紹介していきます。
- 知育子育てを実践したい
- 読書好き、勉強好きな子どもに育ってほしい
- 子どもに伸び伸びと育ってほしい
- 子どもの能力を最大限に伸ばしたい
- 子育てに悩んでいる
- 子どもとの接し方を工夫したい
そんな方は今回の記事が役に立つはずです。
ひとつだけ、
- この記事は父の文章
ということをご留意ください(本記事内の私=父です)。
このブログは以下の方に向けて書いています。
- 子育てをしている方
- (学生・大人問わず)勉強している方
- 子どもと接する機会のある方
よろしくお願いします!
こんな家庭で育った
本題に入る前に、ざっと私の家庭についてご紹介します。
- 父は教育学をしっかりと学んだ人
- 母は褒めるのが上手な主婦
それ以外は、ごく普通の一般家庭ですね。
ごく普通に地元の中高に進んで、大学に行ければ御の字だったようです。
それが人生わからないものです。
受験まみれになってしまうんですね。
当の本人(私)は楽しんで受験していたので、「結果よし」ということで。
↓まずは以下の記事から!
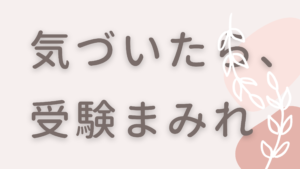
息子視点で教育・子育てについて語る(日本唯一の)ブログです。
親の子育てで良かったこと、役立ったことをどんどん書いていきます。
それでは、父の文章をどうぞ。
勉強のしかたを工夫する
柳川範之さんは、小学4年生までは、日本の小学校に通っていましたが、父親の海外勤務の都合でシンガポールに住むことになりました。
シンガポールの小学校を卒業してから、日本に帰国しました。
その後、日本の中学校を卒業して、父親とともにブラジルに行きました。
ブラジルでは、高校に行かずに大学入学資格検定試験(現在は高校卒業程度認定試験)を受けて、慶応義塾大学の通信教育課程を卒業して、独学で東京大学の大学院に進みました。
現在、東京大学大学院の経済学研究科准教授です。
柳川さんは勉強の仕方を工夫した過程を、『独学という道もある』に書いています。
ノート
中学校での最初の試験のときのことです。
>>>>
「やる気を出して、きちっとノートを作って、しっかり覚えようと思い、それぞれ主要科目について1冊ずつノートを買ってきました。
一生懸命きれいなノートを作り、授業でとったノートをまとめたり、参考書と教科書とノートを照らし合わせていろいろまとめたりしたんですね。
そして、きれいなノートはできるにはできたんです。
あとから見ても、非常によくわかるノートだったと自分でも思うぐらいのものでした。
けれども、実はそのときの試験の結果というのは、あまりはかばかしくなかったんですね。」
>>>>
ふり返って反省してみました。
「ノートを作ることに一生懸命になっていて、ノートの中身をきちっと覚えるとか、中身をきちっと考えるということがおろそかになっていたように思いました。」
そして、
「ノートを作ることよりも自分の頭の中で考えたり、整理をしたり、一生懸命覚えようとしたり、ということに時間を使ったほうがずっといいということ」
に気がつきました。
こうして、まとめノートを作らない勉強方法に変えました。
「ノートというのは書いてしまうと安心してしまうところがあるんです。ノートがないとなれば、しっかり覚えなければいけないという気になるんです。」
しかし、勉強するうえで書くことは重要です。
「ただ書くことによって頭に入ったり、整理をしたりということはありますので、たとえば数学の証明だったら、その証明の図をきちっと書いてみるとか、そういうことはやるのですが、ノートというかたちで残す必要はぜんぜんない、ということになりました。あと暗記的なものは、メモで最後にぱっと見られるようなものを作るくらいにしました。試験勉強の最後の最後に、本当に覚えなければならない重要単語とか重要年号を書いたものだけは作る。」
柳川さんの伝えたいことは、
「だから皆さんノートをとらないほうがいいですよということではなくて、やはり人それぞれいろいろなやり方があるということ」
です。
「ぼくの場合はノートをとらずに自分なりの暗記の仕方とか、頭の使い方をしたほうがずっと勉強の能率が上がったということです。
でも、やはり普通はノートを書いて、きちっとまとめて覚える、ということが一般には言われていますし、それで能率が上がる人は当然いると思います。
ただ、そういう既存のやり方にあまりこだわらずに、少し自分なりのやり方を工夫してみるのもいいんじゃないか、という気がするんですね。」
太田あやさんが書いた『東大合格生のノートはかならず美しい』という本には、東大合格生たちのノートの写真があります。
几帳面にまとめられたノートを見ると、学んだことをまとめる力、整理する能力が、学力を向上させるために必要であることが理解できます。
しかし、柳川さんはそういうふうにしなかったのです。
柳川さんが学者になって、あらためて思うことは、
- 「勉強や研究の自分なりのマスターの仕方を自分なりに工夫することが実はとても大事だ」
と書いています。
「そこをうまくやれると、ずっと早いスピードでステップアップをしていきます。」
問題集
柳川さんはこのように言います。
「問題集の問題をやることは大事なことですが、これも最初の時に失敗したのは、苦労して一生懸命考えて問題を解いていると、時間がかかってしょうがないんです。
何のためにそれだけの時間をかけているのか、という疑問が湧いてきます。
もちろん、時間をかけて一生懸命考えたり、解いてみたりということも必要ですけど、いかんせん(残念ながら)、そこまで学力が届いていないと、無駄に考えてしまうことが多い。
そこで無駄に時間をかけていることがけっこうあることに気づきまして、これじゃいけないと思い、発想を変えました。
極端な言い方をすると、わからなかったらすぐに答えを見る、というパターンで、問題集を使うことにしました。
ただし、単に答えを見て、それですますのではありません。
問題集になぜそのような問題が出ているかといえば、それはそれなりの理由があるわけです。
実は出ている問題と答えがその科目の重要なまとめになっているんですね。
だから、問題集の問題を解きながら、ある程度は考えるにしても、その答えを見て、そこで重要点を把握するという工夫をするようになりました。
そのうちに、これは要点整理に使えるということになったので、逆にある程度割り切って、この1冊は要点整理に使う問題集、こっちはある程度ちゃんと解くのに使う問題集というように使い分けていきました。
最初はなかなか解けない、しょうがないから見ようか、というようなことをいろいろくり返したんだと思います。」
目標
柳川さんは、目標の立て方も工夫しました。
「ぼくが行った工夫の一つは、わりと短めの目標を立てるということでした。」
遠いところに目標があると、やる気を持ち続けるのは困難です。
「たとえば1週間とか、明日はこの辺まで進めるとか、来週はこの辺りまでやってマスターするとか、あるいは1か月さきにはこういうことをやっているというように、わりときめの細かい目標を自分で立てました。」
柳川さんのやり方は、
「長めにせずに短く目標を立て、それに向かってやっていくようにする」という仕方でやる気を持ち続けさせました。
「単に漠然とした目標を決めるだけでは、なかなかやる気が出ない。短期的に、明日これをやると決めておく」
そうすれば、それをなんとかできるように頑張ろうという気持ちになります。
最後に|最強の独学勉強術
ここから、息子のガクが書いていきます。
一人ひとりに個性があります。
物の考え方や捉え方も人によって様々です。
万人に共通する勉強法など存在しません。
自分にあった勉強法を自分で探し出していくしかないのです。
私は中学時代に勉強法の開発に専念していました。
週単位で様々な勉強法を取り入れては、実践→分析→改善のサイクルを回していました。
これによって、脳も鍛えられて論理的思考力の向上にもつながりました。
物事の習得だけではなく、思考力の育成にも勉強法の開発は必須と感じています。
それでは!
↓初めての方はこちらをご覧ください
【無料体験】バイリンガルと自宅で英語レッスン!メディア掲載多数!【お迎えシスター】
![]()
パズル・ロボット・プログラミング、全部できるのは、自考力キッズ
![]()
![]()

母は褒めるの上手
尊敬する父

[体験]全国1300教室の子ども英会話教室|英語で人生を変えよう!
![]()
受験まみれの私
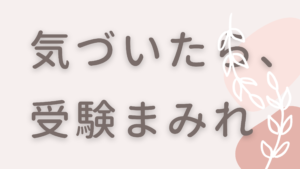
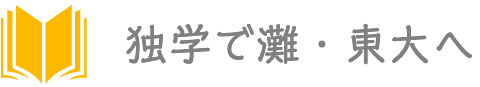


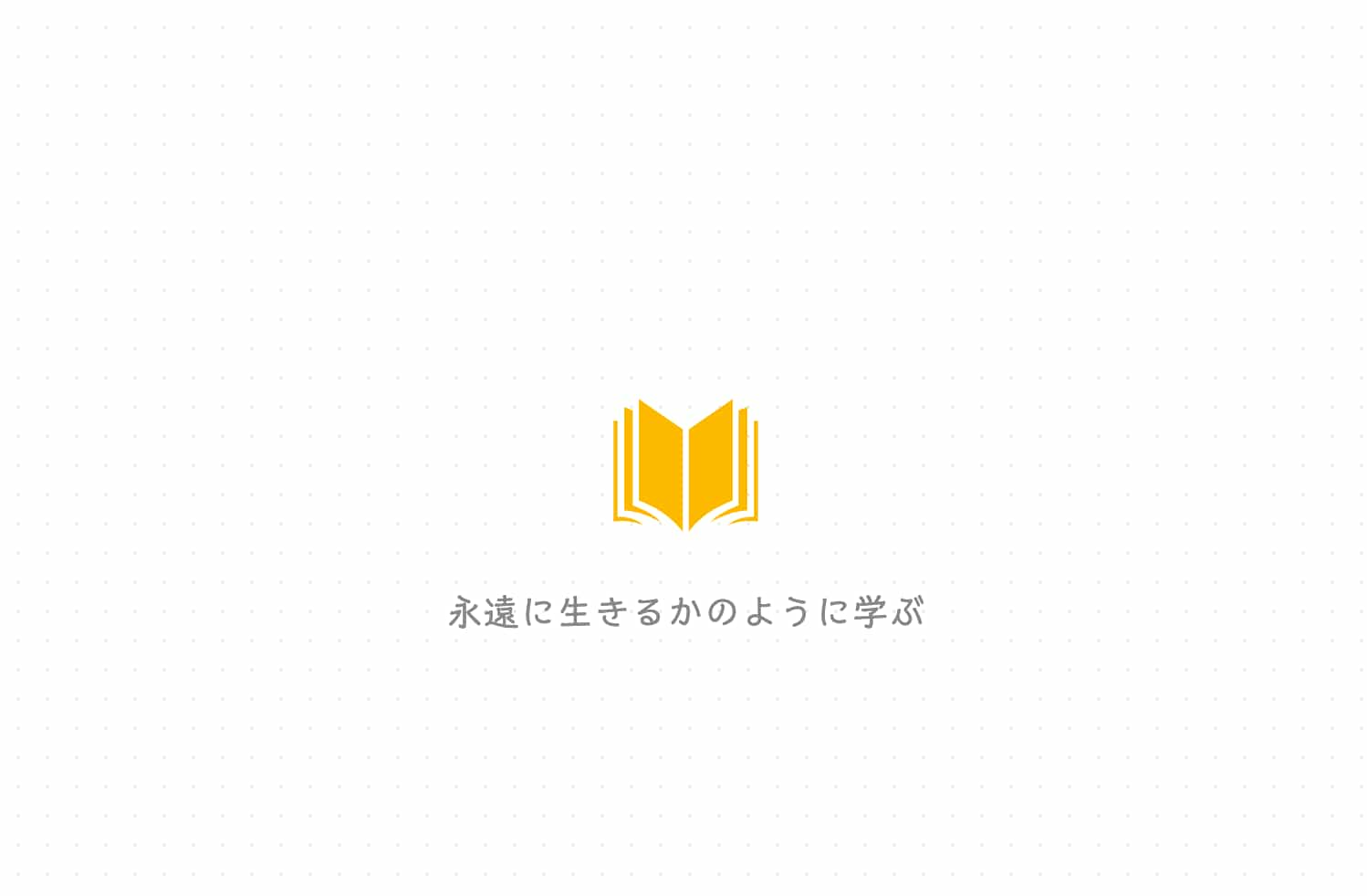

コメント