東大生の私が子供の頃に熱中したもの7つ

よく遊んで、よく学んだ。
私の幼年時代を振り返るとこの言葉につきます。
毎日を精一杯に生きていました。
誰よりも詳しくなろうとしていました。
そして、
誰よりものめり込んで遊んでいました。
むしろ、
遊びからたくさんのことを学んだといった方がいいかもしれません。
それでは、
私が子供の頃にことさら熱中した遊びを列挙していきましょう。
「時期」は私が特に熱中していた期間を示します。
アウトドア
虫とり
時期:0〜11歳
私の子供時代は虫抜きでは語れません。
毎日のように虫取りに出かけていました。

昆虫図鑑は複数買ってもらいました。どのページに何が載っているかも全て記憶してしまいました。
リビングに飼育ケースをずらりと並べていました。それだけでは場所が足りず、玄関や軒先にまであふれていました。昆虫園のようなものを作りたいと本気で思っていました。虫は卵から成虫まで育ててこそ一人前と思っていましたので、一年中このような有様でした。
学校から帰ってくるとさっさと宿題を片付けて自転車に飛び乗ります。虫取り網片手に日が暮れるまで粘っていました。小学2年生の頃から曜日を決めて自主勉強を始めましたが、勉強がない日はせっせと虫取りです。泥まみれになりながら帰宅し、風呂を上がってからも虫を眺めていました。辛抱してくれた母には感謝です(むしろ、私が学校から帰ってくると綺麗な蝶々が羽化したよなどと言って結構楽しんでくれていました)。
山歩き・サイクリング
時期:0歳〜現在
父親の趣味がそのまま乗り移りました。
雨の日も風の日も毎週末のように山に登っていました。

主な目的は昆虫採集と木の実集めです。
実家から山までは一人で行ける距離ではなかったので、休みの日に父と車で通っていました。
連休が取れる時は家族揃ってアルプスの方にも遠出していました。いつもテントを持っていき、山でテントを張って、美しい星空と風景を堪能していました。
自分が根気強くなったのは登山が理由の一つです。
大学に入ってからは山岳部でほとんど毎週末山に出かけています。

また、サイクリングも好きでした。
海にも山にも自転車でいける場所でしたので、心地よい風を受けながらいろんなところに出かけました。小さい頃は、遠出は父と一緒に行くのがお決まりでした。
大学受験生の頃に親からロードバイクを買ってもらい、勉強の息抜きに自転車を本格的にはじめました。そして、一年で自分の住んでいる地域はすべての道を走破しました。
大学入学以降も熱を入れて続けており、宿泊装備を持って遠征します。夏の間は毎朝4時に起きて自転車トレーニングです。
庭いじり
時期:3〜18歳
地方の一戸建てですから、都心部と比べると広い庭がありました。
そこにビオトープを作ったり、小さな雑木林を作ったり、菜園を設けたりしていました。

いわば、小宇宙のようなものです。
幼稚園の頃に山から拾ってきたドングリはわずか数年で大きく成長し、2階の屋根よりも高くなりました。木々が成長すると野鳥が巣を作ったり、たくさんの虫が集まってきたりして、私の夢はますます膨らむばかりでした。
ビオトープ作りは楽しかったのですが維持管理が大変でした。
小規模にしてからは野鳥の水飲み場として、カエルの住処として役立ちました。
家庭菜園は最も生産性のあるものだったため、家族に喜ばれました。
学校に行く前に収穫をするのが私の日課でした。とりわけインゲンは大量に収穫でき、近所にも配っていました。
庭造りも楽しかったです。
飛び石を設置したり、柵を作ったり、DIYっぽいことをしていました。花を殖やすのも好きで、常に花が咲き誇っている庭を目指しました。通りがかりの人に褒められたことを今でも覚えています。
インドア
読書
時期:3歳〜現在
雨の日に冒険するには、読書が一番です。
小さい頃には児童文学作品を読みあさっていました。他にも伝記を好んで読んでいました。
両親から頻繁に絵本の読み聞かせをしてもらっていたようです。特に日曜午後の紙芝居が好きでした。図書館から大量の紙芝居を借りてきてはそれを読んでもらっていました。
さらに、父が大の読書好きで毎日のように書店に通っていました。私の家には書庫として利用している部屋があり、そこには壁一面に大量の本が詰まっていました。学校から帰ってくると毎日新しい本が増えていて、ワクワクしていました。図書館もよく利用していましたが、実際に購入することが多かったです。
折り紙
時期:4〜8歳
図書館に置いてある本は大人用のものも含めて全て借りました。そして紹介されている作品は全て折りました。幼稚園に入る頃に最も熱中し始めて、小学低学年の頃まで続きました。雨の日は家で折り紙をすることが多かったです。幼稚園にも小学校にも自分が作った作品を寄贈して、先生からも喜ばれていました。手先が器用になりました。
LEGO
時期:6〜12歳
灘の同級生に聞いてみると二人に一人以上はレゴに夢中になっていたと答えます。それほど人気なようです。ただし、欠点は高いということ。到底買える金額ではありませんので、全て従兄弟から譲ってもらいました。私の家庭は書籍にはお金を使いますが、おもちゃは全く買いませんでした。そのため、すべて従兄弟のお下がりでした。
レゴのメリットは空間的に物体を把握する力が身につくことです。もちろん、説明書通りに組み立ててもいいです。しかし、工夫を重ねて、自分の設計図通りに自分なりの作品を仕上げる方が何十倍も楽しいです。
工作
時期:3〜18歳
新聞紙から日曜大工まで。
とにかく、ものを作るのが好きでした。レゴもそうでしたが、自分で設計してそれを形にすることがどれほどの歓びを与えてくれるか。それは実際にやった人にしかわからないと思います。私が小さい頃は厚紙や割り箸など、身近なものを用いていろんなおもちゃを作っていました。昭和に発行された昔のおもちゃ図鑑のようなものを見ながら、作りました。幼い頃はcmやmmといった概念さえ理解不能だったため、自分で調べながら解決していました。この繰り返しが算数への興味関心を増していくきっかけになったと思います。
まとめ
モノを作る。
想像を形にする遊びが多かったです。
おもちゃはレゴを除いて与えられませんでしたので、自分で設計して工夫して作り出すしかありませんでした。おもちゃが自分の家にないのは当たり前という感覚でしたので、ことさら不思議に思ったり、友人を羨んだりということは少なかったです。逆に、工夫する能力は非常に高まりました。何でも作ってやるぞという気概を持っていました。
外遊びでいうと虫取りが最たるもので、自然からたくさんのことを学びました。自分にとって最大の先生は自然だと言い切れます。そして、それは今も変わりません。大学に入ってからも自然の作り出す神秘に圧倒されながら研究を進めています。
さらに、登山と自転車は現在も続いており、肉体づくりにも役立っています。父はよく、特技を2つ持てと言っていましたが、自分にとってこれら2つがスポーツの特技と言えそうです。大学山岳部に入部してからは、山の世界が格段に広がり、技術と気力と体力が揃えば、世界を何倍にも広げられることを知りました。
なお、ゲームは所持しておらず、全くの無縁です。これは、個人的にゲームは時間の浪費と捉えているだけであって、別にゲームに熱中している人を否定するつもりはありません。自分の知り合いにもゲームにも研究にも熱中している優秀な人は何人もいます。私の場合は、家の中にこもるよりは外で体を動かした方が気分がいいというだけです。
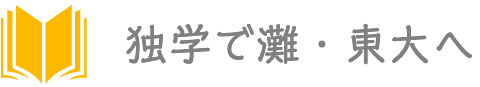

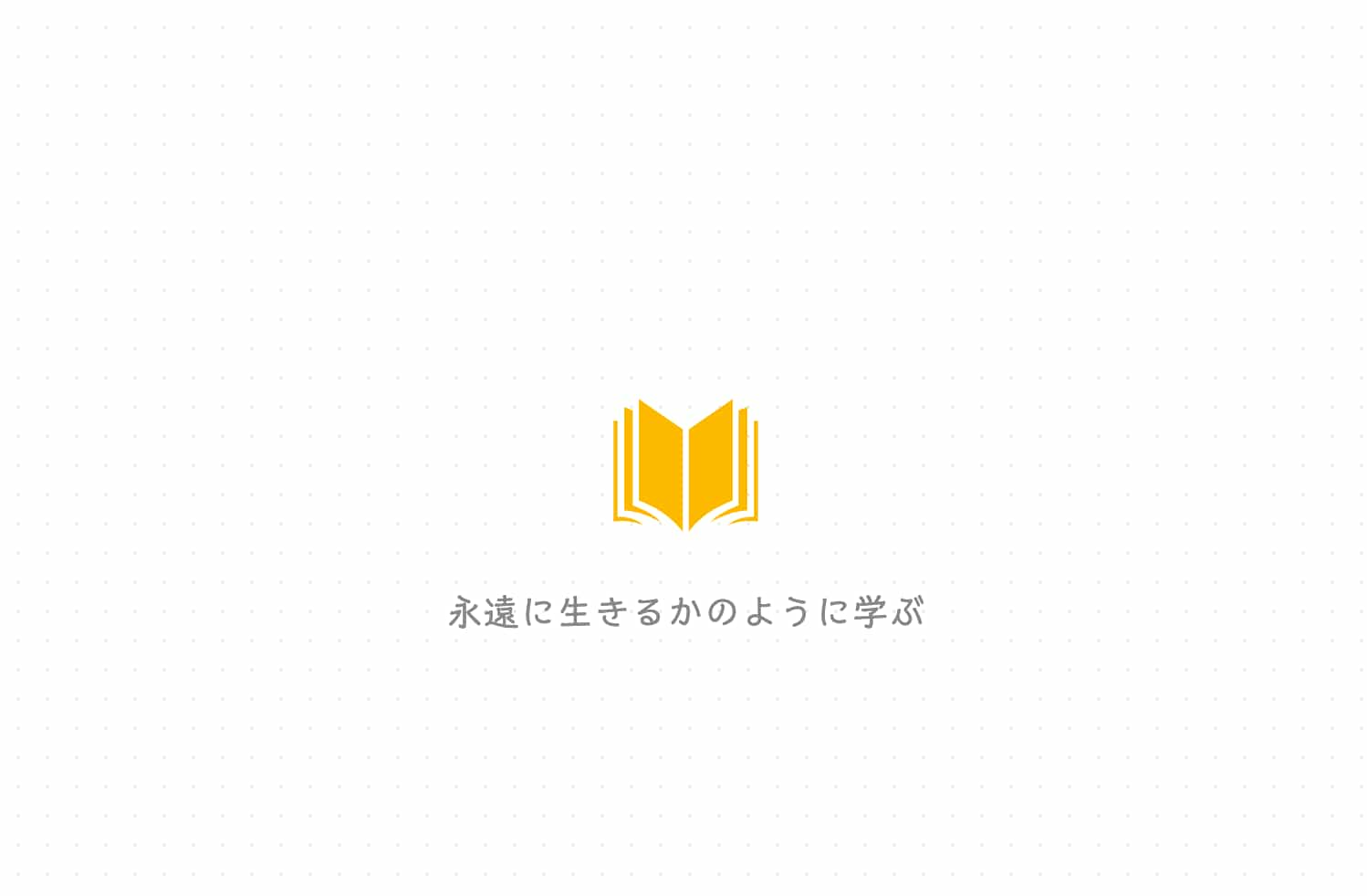

コメント