東大生が解説!いつも選択に失敗する理由|絶対身につけておきたいお金の話
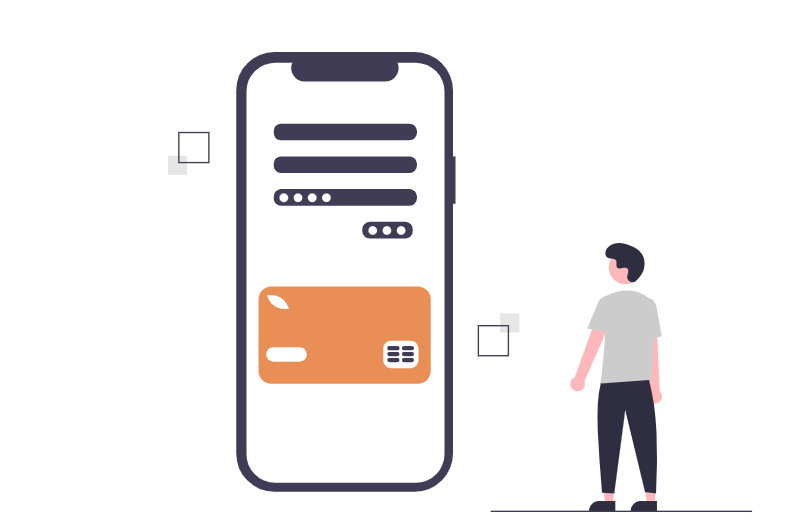
皆さんは普段、どのようにして物事の選択をしていますか?
私は、過去に引っ越しで大失敗をしたことがあります。
すでにハンコを押して、敷金礼金家賃など諸々を支払ってから、物件の不備に気づきました。
払ったお金は戻ってきません。
自分にとっては途方もない大金を失いました。
高性能のMacBook Proが買えたのに…。
冬山の登山装備一式を購入できたのに…。
自動車学校の費用を払えたのに…。
もう、戻ってこないのです。
でも、大切なことを学びました。
それは機会費用とサンクコストという概念でした。
あまりに高い授業料でしたが…。
人生は選択の連続
私たちの人生は選択の連続です。
どの服を着ようか?
食事のメニューはどれにしようか?
といった些細なものから、
進学先はどこに決めようか?
結婚相手は誰にしようか?
といった重大なものまで多種多様です。
これらの選択は予想以上のエネルギーを消耗させます。
よりよい人生を生きるために、
選択を減らす
つまり、
ミニマリズム
といった生き方も注目を集めているほどです。
今回は、選択するために知っておきたいことについて話していきます。
損をしたくない人ほど損してしまうのはなぜ?
心理学の実験によると、
次のようなことがわかっています。
同じ金額で比べた場合、損した時のショックは得をした時の喜びの大きさの2倍以上である。
えぇ?ってなる人もいるかもしれませんし、
あ〜、確かにと思う人もいると思います。
つまり、
金額が同じ買い物でも、私たちはできる限り得しようと考えます。
しかし、
損したくないという気持ちが強すぎると、かえって間違った判断をしてしまい、結果的に損をしてしまうことが山のようにあります。
最善の選択をするための方法
選択の失敗を避けるには、基準を設ければいいのです。
一定の基準に従って機械的にふるいにかければ解決します。
つまり、選択の邪魔となるものを意識的に遠ざけるのです。
それには、次の2点が大切です
- 経済の基本的な知識を身につける
- 皆が陥りがちな心理の罠にはまらない
今回は、行動経済学の重要な概念である、
- 機会費用
- サンクコスト
について解説しながら、最善の選択へのアドバイスを差し上げましょう。
「捨てられない」理由
モノってどんどん溜まっていきますよね。
意識的に処分していかない限り、空間という空間はモノで埋め尽くされていきます。
もったいないからですよね。
食べ物で考えてみましょう。
選択肢が与えられた時、ずっと悩む人っていますよね。
私なんかは、メニューを決めるのが非常に遅いです。
レストランに入るとメニュー表を渡されます。
ページをめくると美味しそうな料理の写真が並んでいます。
あ、これいいなと思います。
でも、さらにページをめくるともっと美味しそうな料理があります。
ましてや、周りを見渡すと他の人がもっと美味しそうなものを食べていることに気づきます。
際限ないですね。
しかし、
選択する=他の選択肢を捨てる
ということです。
何かを選んだら、他の希望は捨てなければいけないのです。
ここで、経済学の重要な概念として機会費用というものがあります。
つまり、
機会費用とは、
あることを行う場合に、もしそれをせずに他のことをしていれば代わりにいったいどれくらいの利益が得られたか
ということです。
例えば、
大学へ行くことの機会費用について考えてみましょう。
それは、
もし大学へ行かずに働くとすれば、同じ四年間でどのくらいの収入を得られるか
に等しいです。
他にも例があります。
時給3000円で働ける人が、100円引きの安売り卵だけを買うために1時間かかったとします。明らかに時間(つまりお金)の無駄遣いをしていると思いませんか?
この場合は、2900円の損になります。
スーパーに並ばずに、働いた方がいいですよね。
もちろん、スーパーに出向くことでママ友と喋って交流を深めたり、運動不足解消になったりと他の面でもメリットがあるかもしれません。
でも、単純化するとこうなります。
まとめ
このように、合理的な選択には機会費用という概念が重要になってきますが、
意思決定において機会費用を考慮する人は少ない
のです。
その時の流れとか感情でなんとなく動いてしまうことが多いんですね。
参考文献
この記事は、『経済とおかねの超基本』という本を参考にして書きました。
必要なお金の知識が丁寧にまとめられており、家庭に1冊あると良いと思いました。
私はお金に疎くて苦労しています。高校生になるまでにざっと読んで基礎知識を身につけた方が良いです。
最近のビジネス書にありがちな、派手なハイライト表示が抑えられているので、読みやすいです。
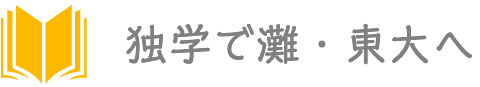

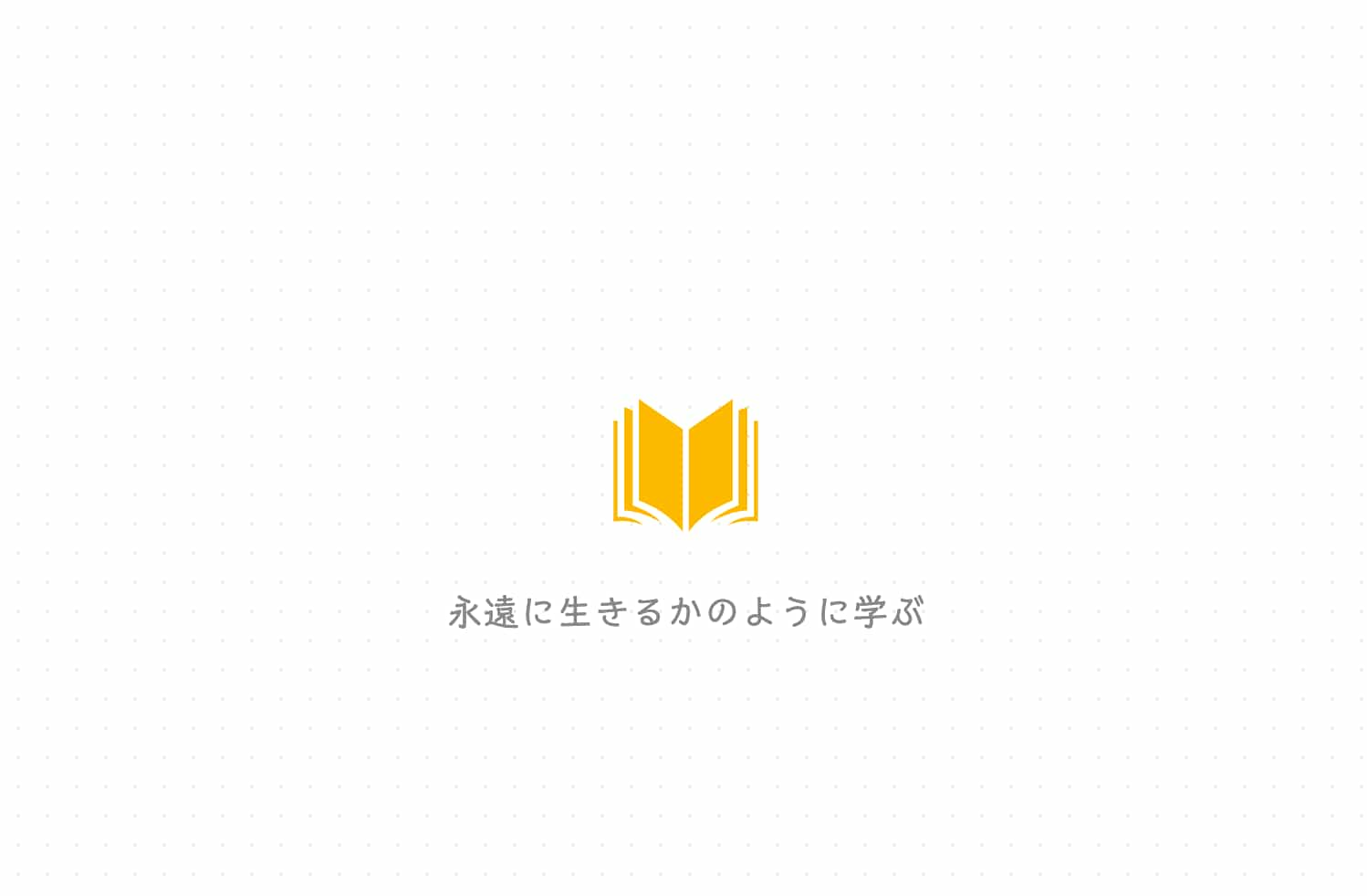

コメント